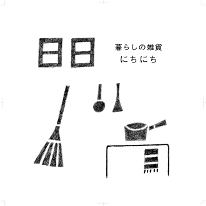掃除機を取り出すまでもないときに重宝する箒とちりとり。1830(天保元)年に創業した江戸帚の老舗・白木屋伝兵衛(東京)に使い勝手のよいちりとり「はりみ」があります。
はりみは、厚紙の芯に竹の枠を張り、和紙に柿渋を塗って「箕」の形に仕上げたちりとり。絶妙のしなりがあることから、床面にぐっと押し付けると、湾曲していた厚紙がまっすぐに伸びて底部が密着。スムーズにゴミやちりを掃き込むことができ、機能性にも優れています。
標準的な大型とテーブルの上のパンくずや消しゴムかすなどを集めるのに最適な小型の2サイズ。紐を通してつるして収納できるように穴も開けられています。セットで使える便利な小箒なども用意されています。
はりみは和紙に柿渋を塗った「箕(み)」のこと。絶妙のしなりがあり、ごみや塵を受けるとき少し押すように持つと底部がぴたりと密着。そこへ箒で掃き込むとすーっと内側へ進みます。いつでもすぐに手に取りやすいから気になる所をいつもきれいに保てます。
厚紙を貼り合わせて柿渋を塗布。外枠に竹をはめ込んでいる。弧の部分竹をぐっと押さえると、床との接地面がピタッとくっつき取りこぼしがない。優れモノ。
江戸箒の生みの親である白木屋伝兵衛は、1830年に銀座で創業した。その後、商人の町・京橋へ移動し、現在も箒一筋に歩んでいる。ホウキモロコシを使う江戸箒は、畳に合った箒で長屋暮らしに適していたため、またたく間に普及した。しかし戦後になると畳の部屋が減り、掃除機が広まるに連れて箒の需要が激減。そこで江戸箒の技術を生かし、テーブル用小箒やサッシ箒など現代の生活に合った箒を開発し、今日に至るまでその良さを伝えている。中でも小回りが利く手箒は軽くて日常でも使いやすく、日本独自のちりとり「はりみ」とセットで使いたい。
はりみは、厚紙を貼り合わせ、柿渋を塗って作った紙製ちりとり。
和紙に柿渋を塗ったもので、しっかりと丈夫でありながら適度にしなる。はりみの底部を押し付けるように当てると、下にピタッと密着。掃き込んだゴミをキャッチ。パン屑の始末も散らかった食卓を最速で片付けてくれる。